日常の運転で、「なにげなくやっている行為」や「ついやってしまう行為」が、
実は交通違反になることがあります。
「知らなかった」では済まされず、反則金や違反点数が科される場合も。
さらに事故やトラブルの原因になることも少なくありません。
今回は、運転中に「ついやりがちな」違反や危険行為を5つ紹介します。
右車線をずっと走り続ける
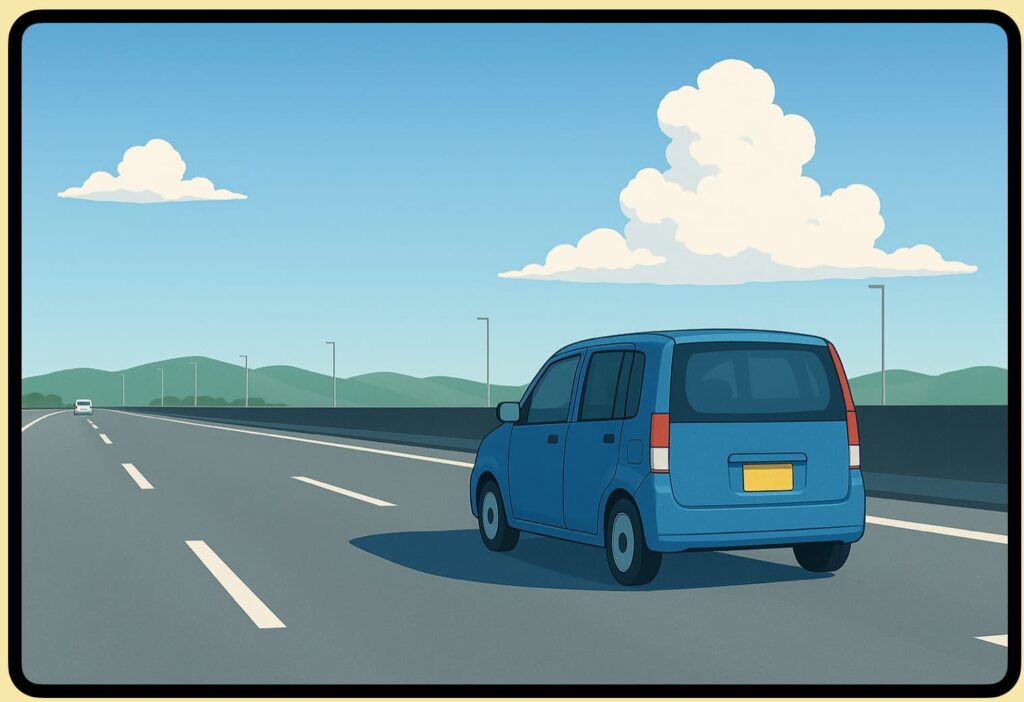
高速道路の右車線は「追い越しのための車線」と定められており、
追い越しを終えたら速やかに走行車線へ戻るのがルールです。
それにもかかわらず、右車線を走り続けると「通行帯違反」にあたり、
反則金は普通車6,000円・大型車7,000円、違反点数は1点となります。
「スピードを出しているから大丈夫」と思いがちですが、後続車に迷惑をかけるだけでなく、
渋滞や事故の原因にもなります。
警察の取り締まりでは「概ね2km以上走り続けると違反と判断されやすい」とされています。ただし明確な距離が法律で決まっているわけではなく、最終的には警察官の判断によります。
フロントガラスにスマホスタンドやアクセサリー

スマホホルダーや小物をフロントガラスに取り付けると、運転者の視界を妨げる恐れがあります。
この状態で走行すると「道路運送車両法違反(保安基準不適合)」や「安全運転義務違反」に問われる可能性があります。
フロントガラスに取り付けて良いのは、車検標章や定期点検ステッカー、ETCアンテナ、ドライブレコーダーなどに限られています。
スマホホルダーやステッカーなどを貼り付けると「不正改造」と見なされ、
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に問われる場合もあります。
さらに、運転中に視界を遮った場合は「安全運転義務違反」となり、
違反点数2点・反則金は普通車9,000円、大型車12,000円です。
わずかな視界不良が事故につながることもあるため、スマホホルダーはダッシュボードやエアコン吹き出し口など、視界を妨げない位置に設置しましょう。
信号待ちでのスマホ操作

信号待ちで停車中にスマホを触ること自体は、直ちに「ながら運転」違反にはなりません。
しかし、完全に止まる前や青信号に変わってから動き出してもスマホを操作しているのは、明確に違反となります。
「ちょっと動いてるだけだから大丈夫」「これくらいならOKだろう」と、
つい自分で勝手にルールを作ってしまう人は少なくありません。
しかしその一瞬の油断が、追突や見落とし、警察の取り締まりにつながります。
青信号に気づかず後続車を待たせる、横断歩道の歩行者を見落とすといったケースも実際に多いのです。
「停車中だから大丈夫」と思い込むのではなく、スマホ操作は必ず安全な場所に停めてから行う習慣をつけましょう。
ウインカーを出さずに車線変更
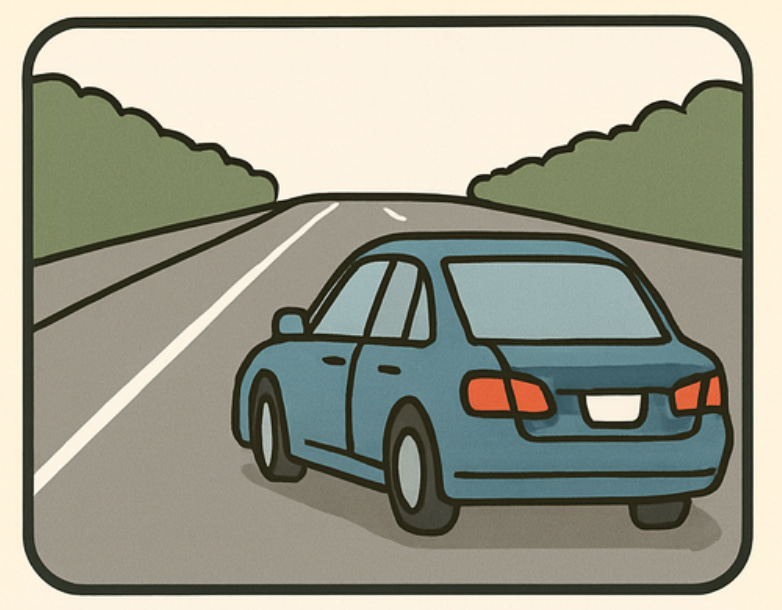
「ちょっとだけだから」「周りに車がいないから」と思って、
ウインカーを出さずに車線変更するのは明確な違反です。
障害物を避ける際も、車体が車線にはみ出す場合は「進路変更」とみなされ、
合図をしなければ違反の対象となります。戻る際も同様です。
法律上は「車体の半分以上がはみ出した場合」に合図義務と解釈されるケースもありますが、
実際には「少しでもはみ出すならウインカーを出すべき」というのが警察や教習所の見解です。
曖昧な基準に頼るより、「必ず合図を出す」ことが事故を防ぐ最も確実な方法です。
「合図不履行違反」に該当した場合は、
反則金は普通車6,000円・大型車7,000円、違反点数は1点です。
周囲から予測できない行動は重大事故の原因になります。
たとえ深夜で他の車が少なくても、必ず合図を出す習慣をつけましょう。
不要なクラクション
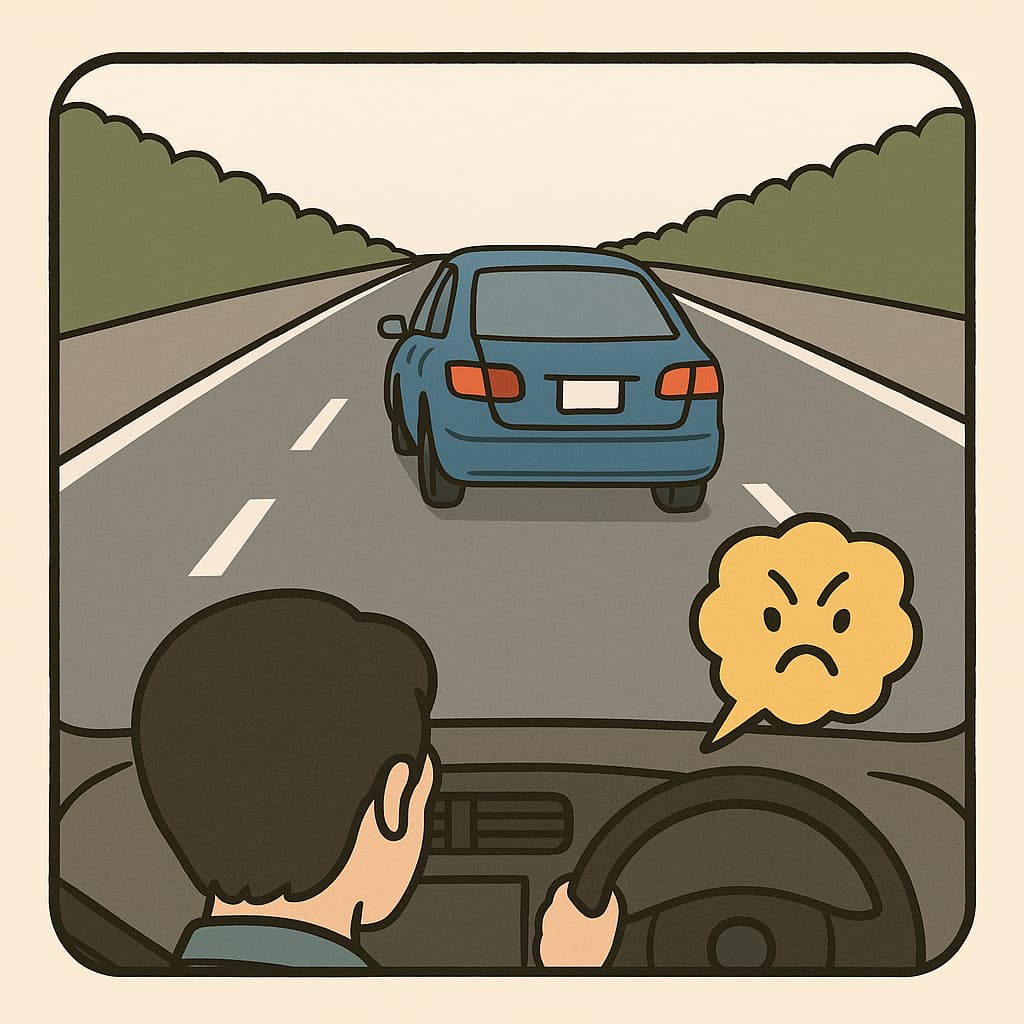
クラクションは「危険を防止するため」に限って使用が認められています。
「早く進め!」といった催促や、イライラをぶつける目的で鳴らすのは「警音器使用制限違反」となり、反則金は普通車・大型車3,000円、違反点数は”なし”です。
「ありがとう」の意味でクラクションを鳴らす“サンキュークラクション”も、法律上は不要な使用に当たり違反となる可能性があります。実際に取り締まりを受けるケースは多くありませんが、誤解やトラブルにつながる恐れがあります。
また「サンキューパッシング(ヘッドライトでの合図)」も本来の使い方ではなく、相手に誤解される危険があります。
クラクションはあくまで危険を回避するためのもの。本来のルールを守ってこそ、安全を守る有効な手段となります。
まとめ
普段の運転で何気なくやってしまう行為でも、実は違反になるケースがあります。
違反は反則金や点数だけでなく、事故やトラブルのリスクを高めます。
「これくらい大丈夫だろう」と思わず、日頃から正しい知識を持って安全運転を心がけましょう。
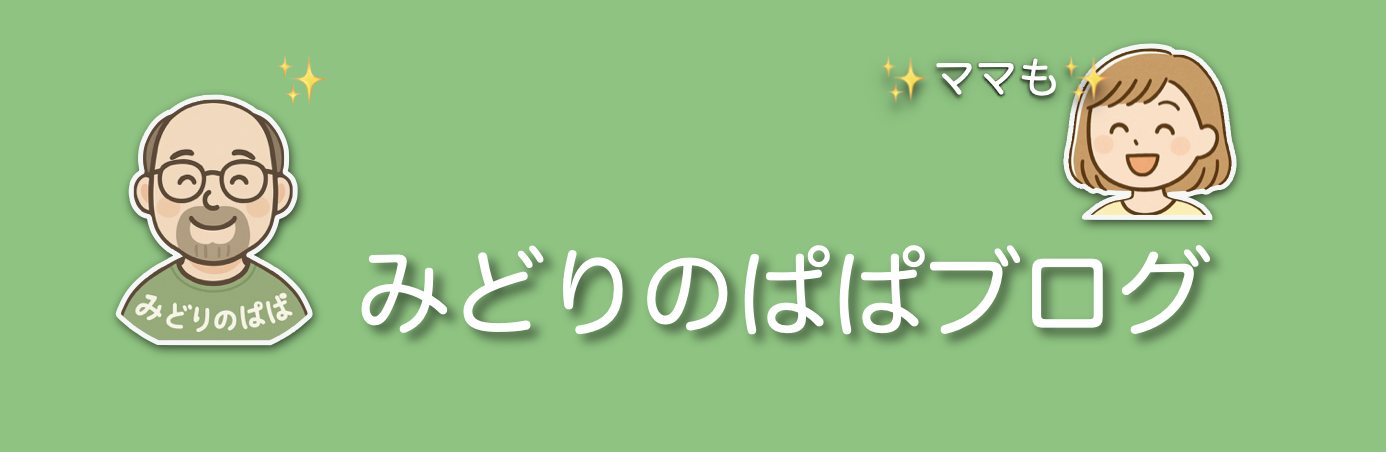
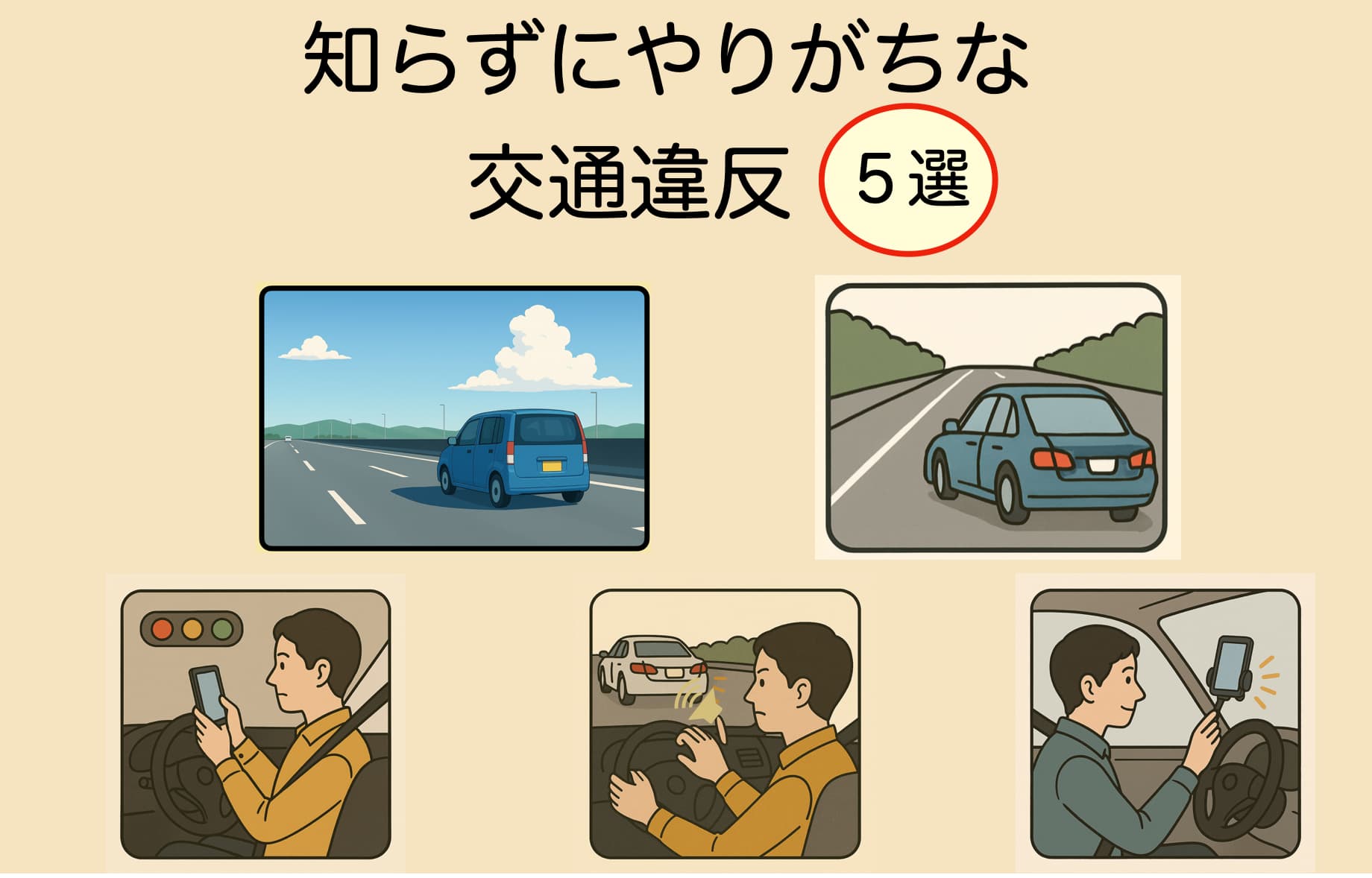

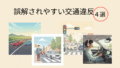
コメント