車を運転していて、どうしても避けられないのが「煽り運転」。
煽り運転にもさまざまなタイプがありますが、
ここでは「車間距離を詰めてプレッシャーを与えてくる」ケースに絞ってお話しします。
煽りにはレベルの大・中・小がありますが、実際に被害にあうと――
怖いですし、正直なところ気分も悪くなります。
私も毎日トラックを運転していますが、しょっちゅう煽られることがあります😓
なぜ煽られるのか?
理由はわかっています。それは「遅いから」🚛…。
そこで今回は、日々トラックを運転する中で「煽り・煽られ」を経験してきた私が、
運転手の目線から「煽られないコツ」をまとめてみました。
初心者ドライバーでも、ここで紹介するポイントを意識すれば、煽られる確率はぐっと減るはずです。
なぜ人は「煽る」のか?
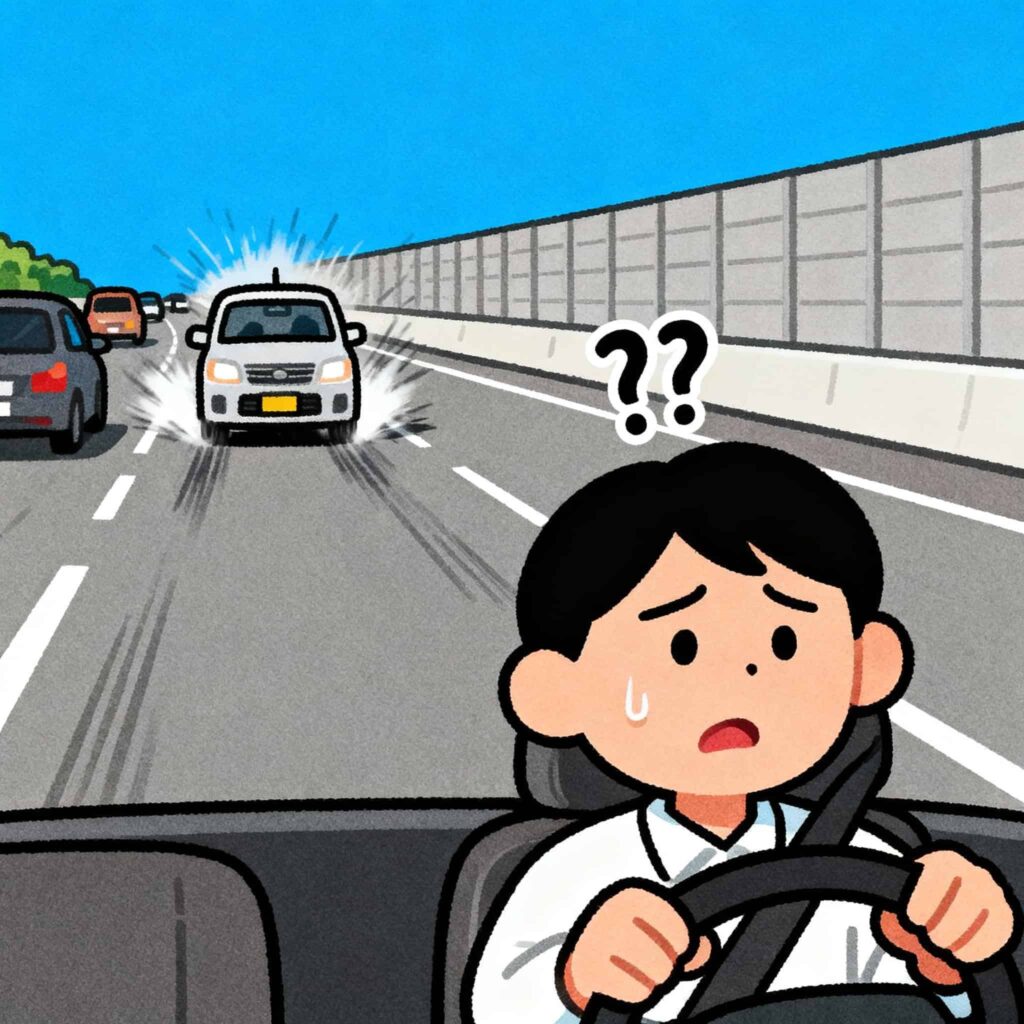
——少し考えてみると…
車を運転していれば、煽る側の気持ちもなんとなく想像できます。
「この車、なんなの!」「何やってんだよ!」「遅いな!」「邪魔だな!」
……こうしたイラッとする気持ちが、煽り運転の始まりです。
だからこそ、相手をイラつかせない運転が大事。
しかし実際には、何も考えず自分のペースで走っている人も多く、
そうなると煽られる確率は自然と上がってしまいます。
相手の「虫の居所」次第では、ほんの些細なことでも煽り被害を受けることがあるのです。
そうならないためにも、「なぜ相手は煽るのか?」
相手の立場で考え、理解しておくことが大切です。
煽る人は、イライラしています。
急いでいるのか、思い通りにいかないのか、
何かしらのストレスが溜まっていて怒りが爆発寸前…。
そんな人のスイッチを入れないように、相手の身になって運転することも
煽られないための重要なコツです。
車間距離を空けすぎない、左車線をキープ
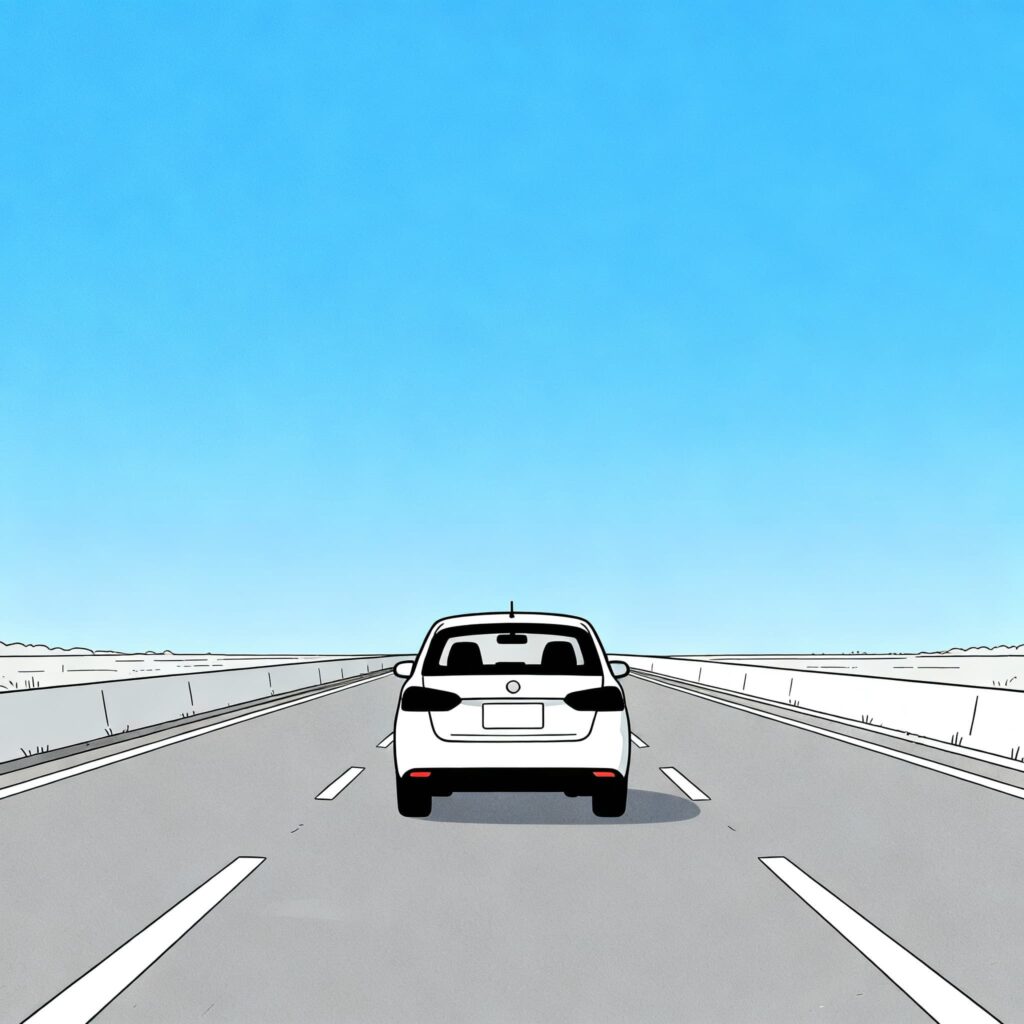
安全運転で一番大切なのは車間距離です。
ただし、空けすぎは煽られる原因にもなります。
車間を大きく空けすぎると、そのスペースに次々と車が割り込んできます。
自分は気にならなくても、後ろの車にとってはイライラの元。
1台入られるごとに不満が募り、2台、3台と続くうちにイライラが増して、
やがて煽り運転へとつながってしまうのです。
これが追い越し車線で起きれば、なおさら危険です。
「自分は遅めに走りたい」「安全のために車間を広くとりたい」という人は、
左車線をキープして走りましょう。
追い越し車線を走り続けることだけは避けるべきです。
右折のために右車線を走らなければならない場合は仕方ありません。
そのときは周りの流れに合わせ、できるだけ邪魔にならないよう心がけましょう。
無理な車線変更はしない、したら速やかに流れに乗る

煽られないためには、車線変更はできるだけ最小限に抑えることが大切です。
「ウインカーを出せばOK」と思っていませんか?
車線変更は、入るスペースや後方の車のスピードに注意しなければ、
ウインカーを出していても煽られる原因になります。
なぜなら、相手にブレーキを踏ませてしまうからです。
流れに乗って走っているときに急にブレーキを踏まされると、誰だってイラッとします。
ですので、十分なスペースとタイミングを見極めたうえで車線変更をしましょう。
そして、変更後は安心せず、素早く流れに合わせて走ることが大切です。
自分の前に割り込まれて、そのままノロノロ走られるとイラッとしますよね。
もうひとつ注意したいのは、車線変更がうまくできず速度が落ちてしまうこと。
これは危険ですし、煽られる原因にもなります。
つまり――
- 車線変更は必要最低限に
- 余裕のあるスペースで行い
- できるだけ早めに目的の車線へ
- 欲張って「こっちの方が早いかも」と頻繁に変えない
これが煽られないためのコツです。
状況を把握して、譲るときは譲る

譲れるときは、気持ちよく譲ってあげましょう。
運転には暗黙のルールがあり、「この場合は譲る」という場面が少なからずあります。
たとえば――
- 本線に合流しようとしている車
- 車線変更したい車
こうした場面で「入れたくない」と意地を張ったり、無関心で譲らなかったりすると、
相手をイラつかせてしまい、結果として煽り運転につながることがあります。
具体的には、本線に入りたい車がいて、渋滞や信号で自分がその前で止まりそうなとき。
そんなときは、スッと譲って先に行かせてあげましょう。
もしそのまま前をふさいで止まってしまえば、相手をイラッとさせ、煽られる原因になりかねません。
車線変更も同じです。
「入れたくない」という気持ちはわかりますが、大きな心で譲ることが大切です。
逆に、速度を上げて妨害するような行為は、煽り運転に発展するきっかけになってしまいます。
嫌な気持ちになるかもしれませんが、
極力譲る姿勢を持つことが、煽られない運転につながります。
交通ルールを守る(暗黙のルールも)

交通ルールを守らないのは当然ながら、暗黙のルールを無視することも、煽られる原因になります。
ただし、この「暗黙のルール」は人によって受け止め方が違うため、難しい面もあります。
たとえば――
- 遅い車は左車線を走る
- 車間距離を空けすぎない
- 不要な車線変更は控える
- 譲れるときは譲る
こうしたものは、明文化されていないけれど多くの人が意識している暗黙のルールです。
一方で、法律で明確に定められているルールもあります。
たとえば道路交通法では、
- 交差点では左折車が優先
- 右折車は左折車の進行を妨げてはならない
と規定されています。
それなのに、右折のタイミングを無理につき、左折車の前に入る車もいます。
すると「こっちが優先だろ!」と左折車が怒り、煽りにつながることも…。
右折は「スキをつく」のではなく、「余裕をもって曲がれる」タイミングで行うこと。
それだけで事故も煽りも防げます。
また、交差点で右折車と左折車が交互に進む光景を見かけることがありますが、
これは左折車の進行を妨げているため、本来は違反行為です。
一見“暗黙のルール”のように見えても、誤った慣習に従うのではなく、
正しい交通ルールを優先することが大切です。
不要なクラクションは鳴らさない

クラクションは法律で使用できる場面が決まっています。
- 危険を防止するため、やむを得ない場合
- 「警笛鳴らせ」の標識がある場所
それ以外でのクラクション使用は違反行為です。
たとえば――
- 仲間へのあいさつの「プッ」
- 「ありがとう」の合図の「プッ」
- 「進め」の催促の「プッ」
- 怒りの「プーーッ!」
これらはすべて本来は違反になります。
特に注意したいのは、信号待ちで前の車が進まないときに鳴らすクラクションです。
これが煽られたと感じさせ、トラブルにつながることがあります。
実際には、つい「プッ」と短く鳴らしてしまうこともあるでしょう。
もし失敗して「プーーッ!」と長めになってしまうと、
相手はムッ💢としてしまい、煽り運転に発展しかねません。
ですので、クラクションは本当に必要な場面以外では極力使わないこと。
これが煽られないための大切なポイントです。
最後に
煽り運転は、実は受け取る側の感じ方次第なところもあります。
実際に、煽り行為をしているつもりはなくても、
相手からすれば「煽られている」と感じることがあります。
中には「自分は煽っていない」と主張するドライバーもいるほどです。
しかし、相手が煽られたと感じた時点で、それは煽り運転と見なされる可能性があります。
最終的にはドライブレコーダーなどの映像をもとに、警察が判断することになるでしょう。
だからこそ、車間距離は自分が思う以上に空けておくこと。
それがトラブルを未然に防ぐ、最もシンプルで効果的なポイントです。
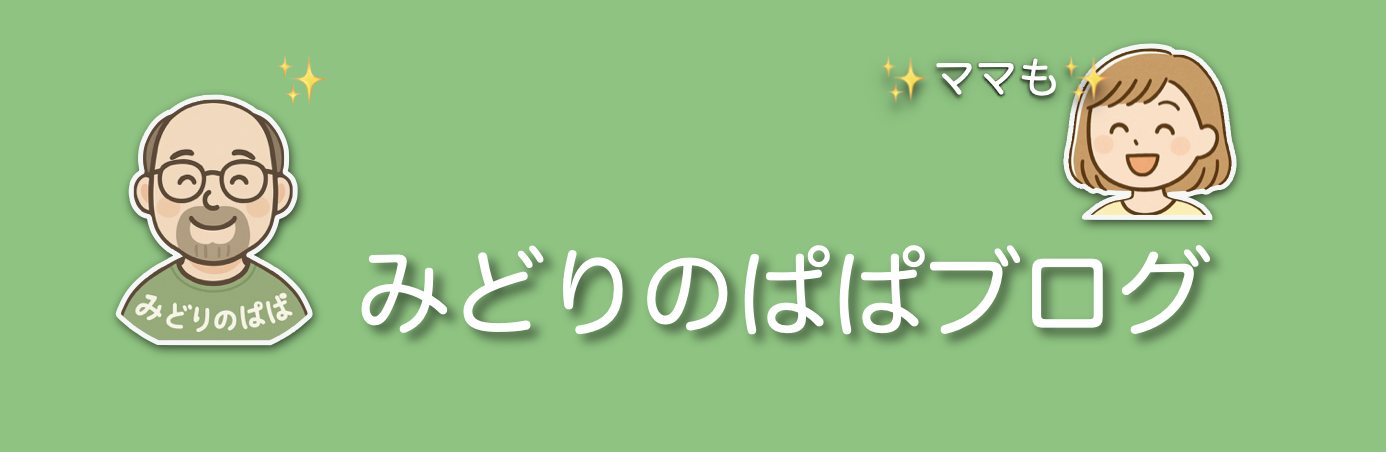



コメント